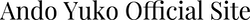【2023/10/11 Release AL『脳内魔法』】オフィシャルインタビュー公開
2023年10月11日(水)リリース 安藤裕子 12th Album「脳内魔法」
オフィシャルインタビュー公開!
Interviewer:柴那典(音楽ジャーナリスト)
デビュー20周年を迎え、自身が立ち上げた新レーベル「AND DO RECORD」からリリースされた通算12枚目の新作アルバム。そこにはクリエイターとして表現領域を意欲的に広げている安藤裕子の“今”が刻み込まれている。前作『Kongtong Recordings』などここ数作に続いてサウンドメイキングのパートナーにShigekuniを迎えた全13曲。大塚 愛「さくらんぼ」のオマージュ曲「さくらんぼみたいな恋がしたい」を筆頭に、ビートルズ、アニソン、ヒップホップなどなど、さまざまなオマージュを感じさせる。硬質な歌詞の言葉の表現、多彩なボーカリゼ―ションもポイントだ。
新作について、自身の今のモードについて、話を聞かせてもらった。
- 柴那典(音楽ジャーナリスト)
2023/10/11 Release AL『脳内魔法』オフィシャルインタビュー
――まず、自主レーベルを立ち上げた理由について聴かせてください。いろんな意図と思いがあったとは思うんですが、どういう経緯だったんでしょうか。
これは一つの理由として語りにくいことで。時代の流れもあるし、自分のやってきた年数もあるし、今の自分のありさまもあるし、いろんな要因があってのことだと思うんですよね。何から語ったらちょうどいいのかな。
――時代の流れというところで言うと?
まず、CDというものの商品としての市場が小さくなってきている。これはもうしょうがないですよね。だけど、それを生業にする企業が、まだ膨張したままで。とてもアンバランスで、ミュージシャンそれぞれが企業と組むということに対しては、分配も考えたりすると、そのアンバランスさに苦しんでるミュージシャンが沢山いる。一方で、自分たちで目の前のお客さんとやりとりしていこうと、独立なさってる方も沢山いて。若い人たちでそこからスタートしてその方が上手くまわっている人も沢山いるし、今まで企業と組んでた中堅以降の人たちもスタイルを変えていこうという人が沢山いる。そういう時代の中で、私はもう若手でもないし、もう散々やってきたものもあって。音楽をお休みしたりする時期もあって、復活以降、自分が楽しいと思う作品しかやらないって決めてたんですよ。そういう流れはきっとあったかなって思ます。
――では、長く活動を続けてきたこと、節目としての今っていうところからすると、どういう感じなんでしょうか。
私の音楽って、変わらないものと、すごく変容しているものが入り混じってるところがあって。一番安定して生業として成立していた頃に出来上がってるシンガーソングライターとしての、どちらかというとバラード歌手のようなイメージと今の自分の違和感みたいなものがあって。私は歌い手よりも作り手なんですよ。常に作っていたいタイプで、終わったら「次は何作ろうかな」っていうところにそわそわしてしまう人間で。いわゆるJ-POPのお手本的なことは散々作ってきたんです。今の私はもうちょっとサウンドに偏ってたり、創作したストーリーを語るっていうことだったり、どんどん私小説的な部分から離れていってる部分もあるし。作り手としての姿形は変わってきている。だから舵取りがだんだん自分に移ってきてると思います。歌謡歌手である時代は会社やプロデューサーがブランディングとか見え方も含め舵を取ってたと思うけど、今はどちらかというともうちょっと素の自分に寄っていっているというのはあるかな。
――そういう意味で言うと、先ほどおっしゃってた休止期間後の2018年の『ITALAN』がやはりターニングポイントであったという感じでしょうか。
そうですね。今のプロデューサーのShigekuniくんとは、ちょうど2017年の終わりくらいから『ITALAN』を一緒に作り始めていたので、そこから6年くらいで、彼とのやり方の中で自分のサウンドも彼と一緒に相談しながら確立していくっていう手探りをしてきて。彼もとても個性的なサウンドプロデューサーなので、私の持ってる部分と徐々に合致して、だんだんとお互いに形にできてきているというのが、ちょうど今ぐらいなんじゃないかなと思います。
――新作はまさに、いろんなオマージュや、いろんなサウンドや曲調へのトライが沢山詰まっている一枚と感じました。そういうものを作ろうという意識は最初からあったんでしょうか。
どうなんだろう。デモ出しって、実は結構長い期間やってて。「こういう曲をやってみたい」とか「こういうのを作ってみた」みたいにお互い投げ合ってた時間が長くて、彼も曲を書いてくれるから。そんなに深く考えてたわけじゃないけど、それで13曲バラバラな曲がいっぱい重なったっていうのがあるかな。
――作り手としていうと、安藤さんの中での曲作りのとっかかりの部分はどういうところが多いんですか?
歌モノと音モノって自分で分けてるんですけど、それによって違いますね。歌モノは純粋に、道を歩いてて口から出てきものを音で膨らましていく部分が多いんです。音モノは、最初にリフを作ったり、リズムトラックを作ったりして、そこに飾り付けをして、ベーシックのデモ作って送ったりする。結構バラバラです。
――打ち込みで曲を作るっていうのは、昔からやってらっしゃったことですか?
歌謡感のあるような時代は歌が中心だったから、歌モノの作り方というか、歩いて出てきた歌をそのまま渡すみたいなことが中心でした。自分は詞と曲を作るのが中心みたいな感じだったので。『ITALAN』くらいから自分の音を作り始めたから、その頃から「こういう音が聴こえたいんだよな」とか「こういう曲作りたかったんだよな」って探り出した感じです。
――新作の曲で言うと、どれが歌モノのクリエイティブ、どれが音モノのクリエイティブの曲という感じですか?
例えば「Family Ties」は、歌に寄ってるものかなって思います。優しいメロディーを優しい言葉で歌いたかったっていうのがあって。「泡の起源」も自分はボーカリゼーションというか、声色の研究というか、そういうものに寄っていたので音にはあまり触れていなくて。「沈澱する世界」もギターで弾き語り的に歌っていたものなので、そのあたりは素直に歌から出てきているものですね。「TikPop」は家でスマホのボイスレコーダーを使ってボイスパーカッションみたいなのを録って、それを取り込んで加工したのをリズムトラックに使ったりしていて。あとは「さくらんぼみたいな恋がしたい」も、自分のシンセの音を残してもらったり、リズムトラックも、私が打ち込んでるTR-808的な音を残してもらったりして、そこにShigekuniくんがアコースティックギターとかを弾いてくれてたり。「猛火の羽」のシンセも私のやつを使ってもらってます。
――安藤さんの打ち込みで作った音を使うものって、ダークというか、アンニュイというか、そういう暗めな雰囲気のものが多くなる傾向があるような気がしましたが。
Shigekuniくんはね、音が明るいんですよ。私は性格は明るいんですけど、根っこにホラーがあるんで、不穏な音が好きなんです。小さい頃にホラー映画が大好きで、特に『サスペリア2』という映画が大好きで。殺人事件が起きる前に童謡が流れているんですけれど、それがだんだん不穏になっていくのが本当に大好きで。殺人現場の古いお家に描かれてた子供の絵をずっと模写しながら、ずっとその曲を歌ってたんですけど、たぶん私の音楽の本当の発端はそこにあると思うんです。市川崑さんの金田一映画も子供の頃からテレビの前に駆けつけて見るくらい大好きで。あれも事件前にサスペンスな感じの音があるんですよね。根っこにちょっとプログレ感があるのか、不穏な感じが染みついていて。私は何の曲でもちょっと不穏な音階を入れたいんです。
――このアルバムでも結構いろんなところに入ってますね。
それがたぶん私の根っこのやつが残されてるやつだと思うんですよね。自分がサウンドを作るようになったら、自分が好きな部分が増していくから、そうしたらだんだん不穏になっていくという。
――アルバムタイトルの「脳内魔法」というのはどこからつけたんでしょうか?
自分の人となりですね。子供の頃から本当に妄想ばっかりしていて。風を操り、風と喋り、生きてたので。魔法使いになろうと思ってたし、人の気を吸い取ったりしてたし。結局、私はそういう、たぶん人の社会で生きてこなかったタイプの人間で。結局またその自分に戻ってきてるというか。ある意味自分らしくどんどんなってきていて。私は夢の中でずっと生きてきたから、それを表現している部分はありますね。
――今おっしゃったことって、歌でもそうだし、さっきおっしゃった音の部分でも表現されてるっていうことなんですね。
そうじゃないかなと思います。なんか、異世界に行きたいんですよ、私は。それは例えば、ライブで歌を歌ってても、毎回その曲の世界に入るんです。だから1曲1曲、自分の表情も全然違うし、ハイテンションで歌った次に号泣していたりするし。それはその世界に行くからであって。私は情緒が安定してないというか、いろんな気持ちで生きてるんです。性格もテンションも変わっちゃう。だからいろんな曲を作りたいんですよ、一定じゃないから。「私、こういう人なんです」っていうのが、あんまりないっていうか。あるとしたら変な奴だってぐらいなんですけど。だからその曲ごとに自分がその世界に行くというか。
――シンガーソングライターって、自分の内面や思っていることを歌って、それが共感されて広がっていくみたいなイメージもありますけど、むしろ虚構の世界とか、物語的なものを作り出して、そこの中に自分が行くみたいなところがある。
そっちが近いですね。世の中で認知された「のうぜんかつら(リプライズ)」という曲も、もともとはもっとポップスで可愛い曲になるはずだったのが、たまたま「デモないですか? 聴かせてください」って言われたそのデモがそのままCMに使われてバラードとして育ったんです。そこからバラード歌手としての依頼が増えて、映画のエンディングだったりとか、バラード歌手みたいなところの役を担うことが増えたんですけど。それでも必ずしも私小説であったかっていうと、そうでもなかったと思うんですよ。依頼されたことから物語を書くのは好きだから、そういう書き方もきっとしてたし。だからいわゆるシンガーソングライター、内省ばかりして、自分のことを私小説として書くっていうところが、全面ではないタイプだとは思います。そういう時代もありますけどね。
――曲についてもいくつか聞ければと思うんですけど、「金魚鉢」に関しては、これは結構前からあった曲なんですよね。
そう。2017年ぐらいですね。おおもとになった「金魚鉢」っていうポエムがあるんですよ。それはもう私がデビューする前、大学生ぐらいの時に、友達がアレンジャーになりたいって、私の曲でデモを作って活動してる時代があって。その時にデモを作ろうって言って、紙ジャケを作って、ブックレットを入れようって言って。写真とか絵とか、そこに散文詩を書いていて。その中に「金魚鉢」っていう詩があったんです。その詩と歌詞の内容は全然違うんですけど、でも見えてるビジョンとしては、その金魚鉢っていう名前に引っ張られて作っていて。私の青春っておそらく90年代に中高生なんですけど、あの当時の渋谷とか、夜のちょっと剣呑とした部分とギャハハとした部分が混ざってる街の中を女子高生が駆け抜けるっていうイメージ。だからもっと若くてヒリヒリしていて。その頃のような、爽やかなエバーグリーンな感じではないけど、ああいう若い魂の持つひりついた青春感というか、そういう部分を歌詞にした曲なのかなと思います。
――この曲は名越由貴夫さんのギターとあらきゆうこさんのドラムが非常にいい味を出していると思うんですが、これも大事な要素でしたか。
そうそう。ライブでやった時にリハでみんなにデモ渡してやってもらって。その時に「ルー・リードだ」みたいな話をしてたんだけど。その時に一緒にやってたのが名越さんとあらきゆうこさんで。そのライブの音源を聴いても、ギターとドラムの抑揚だけで成立してるような感じがして。だからこの曲は2人を呼んで録りたいっていうのは決まってました。あの2人の音がないとなかなか成立しない曲ですね。
――「さくらんぼみたいな恋がしたい」に関してはどうでしょうか。これは大塚 愛さんの「さくらんぼ」へのオマージュということですが、その発想はどういうところから出てきたんでしょうか。
これはたまたまで。私が愛犬の散歩をしていて。公園でぼんやり枯葉にうずくまるのを見てたら、口から「♪私さくらんぼ」みたいな、ちょっと寂しい感じのメロディが出てきて。で、散歩から帰って大塚さんに「ちょっと『さくらんぼ』のオマージュ曲作っちゃった」って送って。「なんやそれ、聴かせて」ってなったんです。で、デモを固めてったら、オマージュ感というか、原曲の引っ張り出し方が、わりとふざけた感じにどんどんなっちゃったから「怒られるんじゃないかな」と「デモ、こんな感じで出来上がってるけど」みたいに送ったら、すごい好きだって言ってくれたから「よかった!」と。それでふざけて「じゃあMVも愛ちんで撮っちゃう?」とか言ったら「出たい出たい」みたいに言ってくれて。事務所スタッフに言ったら「本人が出てくれるなら撮りましょう」って。メジャーレーベルだったら、あり得ない曲なんですけど。
――大塚 愛さんとの関係性ありきだったんですね。
そうですね。ちょっとふざけたこともできたっていうのは、ママ友としての歴史が10年くらいあるのもあったのかなって思います。
――お互い20周年を迎えたタイミングでもありますし、改めて振り返って、同じように歩んできた同期がいるということも、感慨深さがあったりするのかなと思ったんですか。
なんか「20年選手」って、すごいような響きもするんですけど、意外と中堅なんですよ。ちょうど狭間なんです。上の世代もいるし、もちろん若い世代もいるし。30周年、40周年とザラにいるんですよ。だから、どこかの中途半端さは感じていて。たとえばSalyuとかも1年違いだけど、自分たちは、音楽業界が一番変容していった時期に出てきた歌手たちだったから。いろんな栄枯盛衰をみなそれぞれに味わっていて。ありようはそれぞれだけど、それぞれいろんな肌で感じる何かっていうのがあるから。やっぱり会ったりすると、お互いにいろんなことを話し合ったりする機会はありますね。
――「猛火の羽」についてはどうでしょうか。この曲はビートも言葉もすごく攻めたものになっている感じがするんですが、この曲はどういう風にして作ってたんですか。
この曲は私もShigekuniくんも大好きで。この曲は前のアルバム、さらにその前のアルバムぐらいからデモがあったんだけど、その時は入れなくて。でも2人とも大好きで、やりたいよねっていうのがあって、もう一回練り直しました。
――グラウンド・ビート的というか、90年代のR&Bやソウル、ヒップホップに近いゆったりとしたビートと、言葉のソリッドな感じが不思議にマッチしている曲だと思います。
Shigekuniくんもエンジニアも全く同世代なんで、共通言語として合いやすい部分もあるんですね。ヒップホップとしてはそれぐらい前のサウンドになるんだと思うんだけど。そういう硬質でソリッドな音像と言葉で。言葉も近代文学的な固い言葉なんだけど、ボーカリゼーションでちょっと柔和にさせていたり、ハーモニーの音階を和音階っぽくして艶めかしさを出したりして。音像としては私も実験的ですごく好きな曲ですね。
――ラストの「ただララバイ」も90年代のレゲエっぽい感じがあります。「金魚鉢」から始まっていることも含めて、90年代っぽさみたいなものが全般にある気もしました。
そうですね。通してみると、キーワードとして90年代の音楽が沢山会話の中で出てきた1枚だった気がしますね。
――「ただララバイ」はどういう風にして作っていったんですか?
この曲は、江戸屋レコード時代のTOKYO No.1 SOUL SETに『TRIPLE BARREL』ってアルバムがあって、すごく好きなんです。あのアルバムって、当時サンプリングが流行ってて、それをベーシックに曲を作ってるんですよね。「黄昏'95 〜太陽の季節」って曲がすごい好きだから、ああいう感じの郷愁感、仲間との思い出みたいな響きを持った曲にしたいんだって言って。でも私はもうすでにギターでちょっとベーシックの曲を作っちゃってたんですよ。それが裏拍でギターを弾いてたんですよ。それで「もうメロはあるんだけど、これに合うようなサンプリングをつけられないかな」って言ってShigekuniくんにデモを渡したら、彼がそんなに人の話を聞かないってのと、そこらへんの曲を通ってなかったっていうのもあって、デモが返ってきたらレゲエサウンドに犬の鳴き声がサンプリングで入ってて。ちょっとよくわからないなと思ってしばらく眠らせてた曲で。でもこれ、ちゃんと郷愁感とか仲間でいる感じが出ているものになるよって言われて作っていったら、「これ、どっちかと言うとフィッシュマンズじゃない?」ってなって、最後に急にそっちに寄っていったという。
――Shigekuniさんの発想やアイディアで言うと、「星へ帰る」はビートルズへのオマージュの曲ですよね。元ネタが何であるかをあえて隠していない感じがします。
そうですね。わざとはっきりと「ビートルズをやってみよう」という感じでやってますね。音で遊ぼうっていうような一枚なのかと思います。
――音の発想が幅広いだけに、声の表現みたいなところも、やっぱりすごく幅広くなったという実感もあるんじゃないかと思いますが、どうでしょうか。
たしかに、キーも幅もすごい広がって、声色はすごく自由に使えるようになっていて。このアルバムを出してから、歌うまくなったねってよく言われます。曲で言うと、たとえば「ミサイルの降る夜は」は上海租界の箱バンの前で歌うショーの歌手みたいなイメージでレコーディングしてたんですよ。一人で踊って、すごい楽しく録れました。
――アコースティックツアーに関してもお伺いできればと思うんですが、アコースティックツアーのステージで立つ時と、制作の時の自分って繋がってるモードはありますか。それとも切り替えている感じですか?
結構違うんじゃないかな。もともと私のライブって、どこかちょっと演劇感があるんですよ。なぜかというと、やっぱり曲ごとに表現している世界があって、そこに自分が飛び込んでいくようなところもあるので、曲によって全然違うから。演者としてその異世界を見せに行くみたいな感じですね。お客さんも「ミュージカルみたいでした」って感想を仰ってくださる人もいるし、この旅もそういう感じがすごく強くて。でもレコーディング部分に関しては、そこまで感情の没入はなくて。もうちょっと引いて俯瞰して見ている。もうちょっとクリエイターとして、プロデューサーのShigekuniくんと相談しながら構築しているというか。立ち位置がちょっと違うかもしれない。
――演者になる時の自分って、何かが降りてくるとか、曲の世界に入り込むために何かこう自分のマインド意識の部分を変えたりとかありますか。
やっぱり、ざわざわして自分の心が落ち着かないと曲に置いてかれちゃうことがあって。そういう時は焦りますね。形だけどうにか歌ってるような気持ちになって。「怖い、怖い、どうしよう、私これじゃこの曲を歌えてない」と思って、怖くなる。基本はやっぱりその曲ごとに、ちゃんとその世界に降り立ってないと、喉も閉まってうまく声が出なくなるので。
――そうなんですね。逆に、特に今回のツアーで歌っていて、自分としていいところにいける瞬間、たとえば鳥肌が立ったり、自分でグッときたり、そういう時はどんなときですか。
なんだろう、本当それぞれ違うんだけど、例えば今のツアーは20周年を記念した『続:アナタ色ノ街』というライブで、「のうぜんかつら(リプライズ)」とか「海原の月」とか昔の曲ももちろん歌ってるし、新しいアルバムからは、「スキスギてズキズキ」という私なりのアニソンと「Tikpop」と、あと「金魚鉢」と「沈澱する世界」を小編成アレンジでやってて。「スキスギてズキズキ」や「Tikpop」は自分の趣味だから、本当に楽しくなっちゃって。でも「沈澱する世界」ってメッセージソングというか、この世の中をお客さんに問いかけていくっていう曲だから重いシーンに入っていくし。私が最近ずっと好きで歌ってる、「僕を打つ雨」って曲があるんですけど。その曲はストーリーとシーンが確立していて、サウンドもどうあるべきかすごく自分の中ではっきりしてて。そこから「衝撃」という『進撃の巨人』のエンディング曲を歌うことが最近すごく多いんですけど、そこの流れはもう本当にどっか、お客さんがほぼいない状態ぐらい、自分の世界の中で、その2曲はやってることが多いかな。
――「衝撃」という極限的な世界を表現した曲が安藤さんの新しい代表曲になったことで、ライブの幅も広がったような感じがしますね。
そうですね。めちゃくちゃですよ。アニメのアイドルになりたいですってシャカシャカ振りながら歌ってるかと思ったら、本当に地ならしでこの世を潰す、この世の終わりを、怖い顔で歌ってたりしていて。怖い思いをしているお客さんもいると思います。今は戦争も間近にある中で、決して嘘や虚構じゃない本当の怖さっていうものを覚える一曲になってしまってると思うし、あまりの幅広さに見てる人も疲れるんじゃないかなって。でも、だからミュージカルみたいだという感想にもなるんでしょうね。
2023年10月11日(水)リリース
【タイトル】脳内魔法
【収録曲】
01.金魚鉢
02.星へ還る
03.ミサイルの降る夜は
04.スキスギてズキズキ
05.Tikpop
06.猛火の羽
07.さくらんぼみたいな恋がしたい
08. Family Ties
09.あなた色の街
10.沈澱する世界
11. Guardian of Paradise
12.泡の起源
13.ただララバイ
【配信URL】https://ssm.lnk.to/Nonai-Maho
【品番】UCAD-0001
【通常盤価格】紙ジャケット仕様 通常盤 3,500円(税込)
【特典】各法人:ステッカー(先着)
【通常盤WEB販売】
・TOWER RECORD ONLINE
・楽天ブックス
・Amazon
・HMV
・TSUTAYA